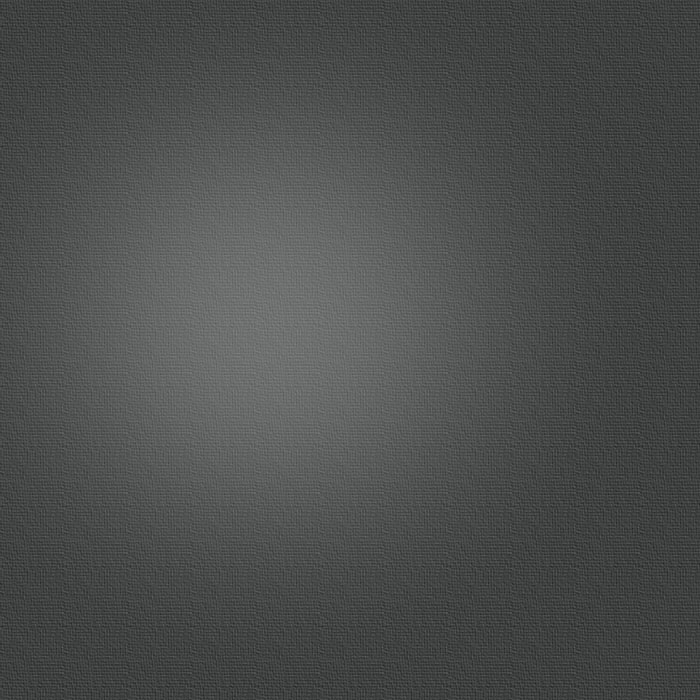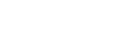Presented by
双眼鏡
1.天体観測用双眼鏡


何と言っても両眼で星空を見るのが一番です。
天体望遠鏡にも双眼アダプターを取り付ければ両眼で観測できますが持っていないのでどんな感じに見えるのかは分かりません。特に大きな口径の双眼鏡で星空を見ると星雲がいっぱい!...気持ちいいものでやみつきになります。
天体観測用の双眼鏡と普通の双眼鏡との違いは
1)大口径、低倍率
2)見掛け視野が広い
3)天頂付近を見られる
とはいえ特別違いはありません。
だけど、レンズ面がミラーの様になった製品があるけどこれではサングラスして星みている様です。
普段はニコンの双眼鏡を使っています。
富士山スターパティでの一コマ
展示された大型双眼鏡
Vixen 120 双眼鏡
富士山スターパティでの一コマ
中古だったけど激安!
ミザール 100 双眼鏡

NIKON
7x50
視野 6,2度

天体観測としてはそれほどの物では有りませんが
無理の無いスペックで視野周辺の色収差が少なく
重宝しています。
2.観望用双眼用
公園などに設置してある双眼鏡です。
大口径の物が多く星空を見るのに適していますが、
天頂付近は見ることが出来ません。
最大の起こしても50度ぐらいです。
さすがにフリーストップでバランスよく取り扱いが楽です。
古いものはレンズがに傷みが発生しているものが多く残念です。


Kowa 20x80
視野3度
静岡県島田市 朝日段公園に設置してある双眼鏡





NIKON製 双眼鏡
口径? 倍率?
静岡県島田市 千葉山 どうだん 山頂の公園に設置てあった

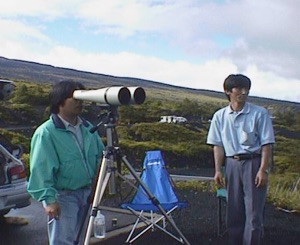
天体観測用として選定する場合どんな点について注意すべきか考えてみます。
1)口径は?
2)見かけ視野は?
3)倍率は?
4)覗きやすさ?
5)色収差は?
6)周辺部の歪みは?
7)プリズムのケラレは?
8)光軸は?
9)ピントは?
口径は50mm以上あるとちょっとした星雲がすぐ判別出来て便利です。
天体観測用途として各メーカーが出している双眼用は50mmx7倍が定番です。
大昔天文ガイドではこのクラスの双眼鏡ばかり取り上げて性能比較調査をしていました。
確かに大きさと言い見え方と言い申し分ないクラスです。
バードウオッチングではもう少し倍率がほしい所で、最近では50mmx10がメインのようです
このサイズは丁度 暗い所で瞳が開いた時の瞳径とと双眼鏡の射出像の大きさがほぼ同じ(5mm)になり
夜間の観測向きと言えます。(昼間は瞳が狭くなるので絞りを入れたようになり口径の恩恵を受けません)
3.双眼鏡の選定
見掛け視野が広い双眼鏡は像が甘いとよく言われます。
ありえない値段で広角をうたう機材はちょっと心配ですが、広角というと65度以上の物を指すようです。
確かに60度を超える機材は覗いていて飽きが来ません とても開放感が有って気持ちいいです。
中には80度を超えるものもあり、第二次世界大戦中にはドイツ軍で見掛け視野が120度の双眼鏡が有ったと言われています。 是非覗いてみたいものです。
現在使っている双眼鏡は実視野6.2度で見掛け視野43度くらいなので少々狭い感じが否めません その分無理なく色収差も程よく良い機器と思います。
随分前ですが、某カメラ屋さんでカートン光学の50x7視野7度の双眼鏡(アドラブリック双眼鏡)を見せてもらった事があります、1度の違いがこんなに開放感を与えるのかと驚きました また非常に軽量で是非欲しいと思いました..当時5万円ほどだったと記憶しています。
残念ながら製造メーカー(宮内光学の廃業により)の都合で現在は販売していないようです。
天体観測専用なら低倍率で広角が良いのですが地上用と併用する場合低倍率では物足りない気がします。
新聞広告で100倍を誇らしげにうたう広告が有りましたが固定でもして見ていないと
手ブレで揺れすぎて見えないと思いました 使ったこと無いので分かりませんが酔いそうです。
極端に明るい月ならクレーターの観測に良いかもしれないです。
天体用途では敬遠されがちですが、ズーム式も悪くは無いと思います。
ズーム式は光学的に複雑な上に像が甘くなりがちですが、目視用途と割りきって考えれば良い選択かもしれないです。低倍率の時視野が狭いなどのウイークポイントを踏まえておく必要が有ります。
双眼鏡を三脚に固定して観測するのならアイポイントがある程度遠い方が覗きやすいですが
小型の場合固定しないで、ほとんど目にあてがって使う場合遠すぎると使い難いです。
昼間使う場合横から光が入り込むと見にくいので横からの光を遮断するアイキャップが有ります。
メガネをかけている場合アイキャップ越しに見る事になりアイポイントが合いません
アイキャップが収納式だったり外したり折り曲げ出来る構造になっている物が有ります。
白いものを見ると縁に青いロハ(影)が出ます、これが色収差で明るいほどはっきり出ます。
極端に酷いものは反対側に赤いロハも出ます。 ある程度は仕方ないのですが見比べて強く出るものは
避けたほうが無難でしょう。
広角の物ほど近くの物を見ると周囲に放射状の収差が発生します。
これもある程度しかたない物ですが視野角の狭い機種はこれが小さいのでどちらを採るかになろうかと思います。
双眼鏡を明るい所でかざして見ると接眼部に瞳径が見えます。プリズムを使用している双眼鏡は
更にこれをよく見ると周辺にグレーの影が見えます 赤い光が屈折しきれずかけてしまう現象です。
(BaK4ガラスのプリズムを使用している機種はこの現象が出ません)
実際には瞳径の周辺なのでさほど影響有りません。

初めて覗いた時など左右の像が一致しない事が有ります。
左右の場合、単に目の間の距離(瞳孔間距離)(PD)とアイピース間の距離が合ってない場合が有ります。
双眼鏡によっては調整範囲が狭いものや鼻と干渉して見にくい場合があるので顔に合う機種選択も重要です。
像のズレが上下にある場合致命的です。
強いショックを与えたなど光軸がズレた場合メーカーでも修理出来ない事が有るので極力収納ケースのしっかりした機材を選びたいです。
ピント調整は大きく分けて2種類有ります。
1)アイピース単独で2箇所にあるもの
2)センターフォーカス式で中央に1箇所と左右どちらかのアイピースに微調整があるもの
アイピース単独のものはフォーカスを調整する毎に両方の調整が必要なので遠くを見たり近くを見たりする場合
不便に感じます。 天体用途では無限に合わせておけば一定なので問題有りません、またこの機種は多くが防水型であることも特徴です。
センターフォーカス式は鏡筒と鏡筒の間にフォーカス機構を持ったもので比較的この方が一般的です。
高級な双眼鏡は対物レンズとアイピースの間にフォーカス用のレンズがあり内部で移動しますので
外から見ても外観が変化しない構造の物もあります。
特に地上観測でも使用する場合はフォーカスがスムーズに調整できるかもポイントです。
フォーカスノブが硬かったり柔らかすぎると使いにくいものです。

公式や数式を入力すると式を解析して
逆算、穴埋め計算するアプリです。
答えから式の構成要素を逆算するので
公式を逆展開しなくてもOK!
ローン計算や割り勘計算から電気計算
なんでも来い!
例えば売値から元値や割引率を逆算出来ます
intelli-Calc
iPhone & iPad
Application
モールス信号を学習する機能をコンパクトなiPhoneに実現しました。
通勤の移動中にも学習することが出来ます。
モールス信号音をマイクで拾って文字列に復調することも出来ます。
intelli-Morse
iPhone Application
iPhoneのマップを使って建造物の面積、距離を計測します。
任意の2箇所にピンポイントを設定するとピンの位置からその距離を計測、同様にピンを使って範囲指定すると面積を算出します。
測定点と情報は保存し一覧表から選択し再現表示することが出来ます。
GPSString
iPhone Application
<<無料公開中>>